 |
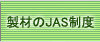 |
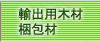 |
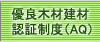 |
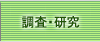 |
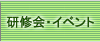 |
 |
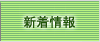 |
1.木材のJASについての質問と回答
A1
A1
A1
A
A
A1
A1
A1
A1
A1
A
2.輸出用木材こん包材についての質問と回答
A1
A1
A1
A1
| Q 1-1 JASとはどのようなものですか。 |
JASとは、日本農林規格の英訳「Japanese Agricultural Standard」の頭文字をとっ
た略称で、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」に基づいて、制定した規格のことで、現在では制度全体をあらわす言葉としても使われています。
2
この制度の目的としては、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資し、もって農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産物等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することがあげられています。
3
この法律で「農林物資」とは、飲食料品及び油脂、農産物、林産物、畜産物並びにこれらを原料または材料として製造し、加工した物資であって政令で定めるものとされています。
4
JAS制度は、次の2つの制度からなっています。
[1]
JAS規格制度
農林水産大臣が制定した品質基準及び表示基準(日本農林規格)による格付に合格した製品にJASマークをつけることを認める制度。
農林水産大臣が制定した品質基準及び表示基準(日本農林規格)による格付に合格した製品にJASマークをつけることを認める制度。
[2]
品質表示制度
一般消費者の選択に資するため、特定の品目の農林物資についてすべての製造業者等に、農林水産大臣が制定した基準による品質に関する適正な表示を義務付ける制度。ただし、木材関係には、品質表示制度に関したものがありません。
一般消費者の選択に資するため、特定の品目の農林物資についてすべての製造業者等に、農林水産大臣が制定した基準による品質に関する適正な表示を義務付ける制度。ただし、木材関係には、品質表示制度に関したものがありません。
| Q 1-2 木材関係のJASにはどのような種類(規格)があるのですか。 |
木材関係のJAS規格は、次の9品目があります。(農林水産省・JAS規格一覧【林産物】から)
2
| 規格名称 | 制定年月日 | 最終改正 |
|---|---|---|
| 製材の日本農林規格 | H19.8.29 | - |
| 枠組壁工法構造用製材の日本農林規格 | S49.7.8 | H22.7.9 |
| 集成材の日本農林規格 | H19.9.25 | - |
| 枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格 | H3.5.27 | H22.7.9 |
| 単板積層材の日本農林規格 | H20.5.13 | - |
| 構造用パネルの日本農林規格 | S62.3.27 | H20.6.10 |
| 合板の日本農林規格 | H15.2.13 | H20.12.2 |
| フローリングの日本農林規格 | S49.11.13 | H20.6.10 |
| 素材の日本農林規格 | H19.8.21 | - |
製材の規格では、「造作用製材」、「構造用製材」、「下地用製材」、「広葉樹製材」があります。
3
枠組壁工法構造用製材の規格では、「枠組壁工法構造用製材」、「MSR製材」があります。
4
合板の規格では、「普通合板」、「コンクリート型枠用合板」、「構造用合板」、「天然木化粧合板」、「特殊加工化粧合板」があります。
5
集成材の規格では、「造作用集成材」、「化粧ばり造作用集成材」、「構造用集成材」、「化粧ばり構造用集成材」があります。
| Q 1-3 JASマークの表示はどのような手順で行われるのですか。 |
製品(農林物資)をJAS規格により格付し、JASマークを表示することができるのは、登録認定機関から認定を取得した認定事業者だけです。
2
認定を取得した認定事業者において、当該製品がJAS規格に適合しているかどうかを検査し、その結果JAS規格に適合していると判定・格付した製品にJASマークを表示(格付の表示)して販売することができます。
JASマークを表示するかどうかは、事業者の任意です。
3
JASマークを表示するかどうかは、事業者の任意です。
工場等で製造される製品の格付けは、[1]試料の抜き取り(サンプリング)、[2]その検査(テスティング)、[3]判定結果に基づくJASマークの表示(ラベリング)の3つのプロセス業務からなります。
これらの業務についてAタイプ認定事業者はその全てを自ら行うことができます。Bタイプ認定事業者は、[2]の検査業務を第三者検査機関に委託して、その結果に基づいて自らJAS規格に適合していると判定・格付した製品にJASマークの表示を行います。
4
これらの業務についてAタイプ認定事業者はその全てを自ら行うことができます。Bタイプ認定事業者は、[2]の検査業務を第三者検査機関に委託して、その結果に基づいて自らJAS規格に適合していると判定・格付した製品にJASマークの表示を行います。
認定事業者は、大量・連続生産方式をとる関係からJAS格付けの前にあらかじめ
JASマークを製品に表示することも認められています。ただし、この場合にもJASマークの表示が格付の結果と一致したものでなければ、JASマークを表示して販売することは許されず、もし、格付けの結果が不合格になった場合には、JASマークを除去しなければなりません。
5
登録認定機関は、一定の基準(ISO/IECガイド65等)に適合する法人で、国に登録した者です。
林産物の登録認定機関については、ホームページ「製材のJAS制度」/1.JAS制度の概要を参照してください。
林産物の登録認定機関については、ホームページ「製材のJAS制度」/1.JAS制度の概要を参照してください。
| Q 1-4 | JAS認定事業者(認定工場)の対象範囲が拡大されたと聞きましたが、どのような事業者が対象になるのですか。 |
製材JAS認定事業者(製材等)の対象について、法律の改正前は、製造業者(製材工場)が対象でしたが、平成17年6月の改正(平成18年3月施行)において、製造業者に加えて、製造工程を管理し、かつ、製材品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者又は輸入業者も、製造業者を特定した上で、その製造業者ごとに登録認定機関の認定を受けてJASマークを表示することができることとなりました。
また、日本へ製材等を輸出する外国の事業者も同様にしてJASマークを表示することが可能となりました。
また、日本へ製材等を輸出する外国の事業者も同様にしてJASマークを表示することが可能となりました。
| Q 1-5 | JAS認定事業者にはAタイプ、Bタイプの二つのタイプがあると聞きますが、どのように分類されるのですか。 |
「Aタイプ認定事業者」は、認定の技術的基準(製造設備、検査設備、品質管理体制、格付体制、内部監査体制等)を満たし、認定を受けた対象製品について、自ら検査、判定・格付を実施し、JASマーク表示が行える認定事業者です。
「Bタイプ認定事業者」は、認定の技術的基準のうち、格付検査担当者の資格を有するものを置かない等の理由により、自ら格付のための試料の検査を行わず、検査を外部の「第三者検査機関」に依頼し、その結果に基づいて判定・格付を実施してJASマーク表示を行える認定事業者です。
「Bタイプ認定事業者」は、認定の技術的基準のうち、格付検査担当者の資格を有するものを置かない等の理由により、自ら格付のための試料の検査を行わず、検査を外部の「第三者検査機関」に依頼し、その結果に基づいて判定・格付を実施してJASマーク表示を行える認定事業者です。
| Q 1-6 | 「第三者検査機関」とはどのような組織ですか。また、この機関はどこに所在しますか。 |
「第三者検査機関」は、格付のための試料の試験・検査を行う機関です。
この機関は、検査を適正に行い得る機械器具及び人員を有し、その人員は検査を公正に実施しなければなりません。
なお、「第三者検査機関」がBタイプ認定事業者の格付のための検査業務を実施するためには、登録認定機関(全木検)の許可が必要です。
2
この機関は、検査を適正に行い得る機械器具及び人員を有し、その人員は検査を公正に実施しなければなりません。
なお、「第三者検査機関」がBタイプ認定事業者の格付のための検査業務を実施するためには、登録認定機関(全木検)の許可が必要です。
製材関係の第三者検査機関は、現在、北海道を除く46都府県木(協)連のうち、Bタイプ認定事業者の所在する44府県木(協)連と全木検の45機関です。
なお、北海道については、北林検が第三者検査機関です。
なお、北海道については、北林検が第三者検査機関です。
| Q 1-7 | 認定事業者の要件の一つとして品質管理及び格付を担当する資格者の配置が必要と聞いていますが、何人必要なのか。また、資格はどうすれば取得でき、資格には有効期間がありますか。 |
製材についての製造業者等の認定の技術的基準において認定工場等に配置すべき品質管理を担当する者及び格付を担当する者の資格及び人数が定められています。
Aタイプ認定事業者は3名以上、Bタイプ認定事業者は2名以上の資格者が必要です。
なお、人工乾燥材については上記資格者のほか、木材乾燥士または針葉樹製材乾燥技術者の資格者1名以上、また、保存処理材については、木材保存士の資格者1名以上が必要です。
2
Aタイプ認定事業者は3名以上、Bタイプ認定事業者は2名以上の資格者が必要です。
なお、人工乾燥材については上記資格者のほか、木材乾燥士または針葉樹製材乾燥技術者の資格者1名以上、また、保存処理材については、木材保存士の資格者1名以上が必要です。
品質管理及び格付を担当する資格者は、登録認定機関全木検の実施する「認定の技術的基準に係る資格者養成等研修会」の研修修了者(合格者)で、全木検に登録された者です。
資格者は、研修終了後3年毎(更新)に技能研修を受講する必要があります。
なお、資格者養成等研修会の開催日等については、全木検のホームページでお知らせします。
資格者は、研修終了後3年毎(更新)に技能研修を受講する必要があります。
なお、資格者養成等研修会の開催日等については、全木検のホームページでお知らせします。
| Q 1-8 JAS製品にはどのようなメリットがあるのですか。 |
JASの目的は、品質を保証し、消費者を保護するということですので、生産者、消費者相互にメリットがあるといえます。
2
特に、平成18年の建築基準法の改正において、建築物の安全性確保を目的に建築確認・検査の厳格化が求められることになりました。
具体的には、建築物の構造計算適合性の判定の義務化、構造設計等の適正化、瑕疵責任履行の確保などです。
このことから、木材等の建築材料においても従来以上に品質・強度の基準に適合したJAS製品が求められることになると思われます。
3
具体的には、建築物の構造計算適合性の判定の義務化、構造設計等の適正化、瑕疵責任履行の確保などです。
このことから、木材等の建築材料においても従来以上に品質・強度の基準に適合したJAS製品が求められることになると思われます。
JAS製材は、用途別に規格化されています。
例えば、目視等級区分構造用製材の甲種構造材の規格は、主として曲げ性能を必要とする部材、即ち建築物の梁、桁等の横架材用としての品質基準を定めています。
4
例えば、目視等級区分構造用製材の甲種構造材の規格は、主として曲げ性能を必要とする部材、即ち建築物の梁、桁等の横架材用としての品質基準を定めています。
JAS製材では、製品寸法とその許容差が製品の用途や含水率に応じて決められています。更に、人工乾燥処理材の含水率が柱材や造作用材など用途に応じて決められています。
5
JAS製材では、木材の樹種、薬剤の種類に応じた保存処理基準が設けられていて、用途別に最適なものを求めることが出来ます。
6
JASの構造用製材の樹種、等級に対応した国土交通省による基準強度(H19.11.27国土交通省告示第1452号)が規定されていて、強度性能が明確にされています。
7
製材JASでは、表示すべき事項や表示方法が規定されており、違反した場合の罰則が法律で厳しく定められています。
| Q 1-9 | 認定事業者の認定は、どのように行われるのですか。また、認定事業者の義務等はどのようなものですか。 |
認定の手続きについて
2
| ① | 申請書の作成: 申請者は、認定のための「申請書」、工場施設等に関する「付属書類」及び認定事業者として実施すべき事項の「同意書」を提出します。 全木検は、申請等に必要な認定情報を提供します。 |
| ② | 申請の受付: Aタイプ認定事業者の申請は、登録認定機関である全木検が受け付けます。Bタイプ認定事業者の申請は、各都府県木(協)連に駐在する検査員・審査員が受け付けます。 原則として、申請書を受理した時点で、認定手数料等を請求します。 |
| ③ | 書類審査: 申請書を認定の技術的基準に基づいて審査します。 |
| ④ | 実地調査と製品調査: 書類審査で基準に適合していると判定した場合、事前に調査計画を通知して、製造工場等の実地調査を行います。同時に、製品の材面検査及び性能検査を行います。 |
| ⑤ | 認定の判定と登録、公表: 実地調査及び製品検査の結果、基準に適合していると判定した場合、認定通知書と認定証を交付します。同時に、認定に際し遵守すべき事項と認定事業者の義務を書面で提示します。 併せて、認定事業者をホームページ等で公表します。 |
認定申請者の登録に際し遵守すべき事項について(一部)
3
| ① | 認定の基準: 全木検は、認定の技術的基準の要件を満足した事業者を認定します。 |
| ② | 認定の維持、拡大、縮小等: 認定の有効期限はありませんが、年1回の定期監査において認定の技術的基準に基づく調査及び製品検査の結果、基準に適合していると判定した場合に認定の維持を認めます。 認定の品目の拡大、縮小及び機械施設等の変更に伴う追加変更審査においても同様です。 |
| ③ | 格付業務の停止又は格付品の出荷停止等: 定期監査等において、全木検が是正を請求したにも拘らず、指摘した不適合事項を是正するのに相当な期間を要する場合は格付業務の停止、又は期限を定めて格付品の出荷の停止を命じます。 |
| ④ | 認定の取消し: 指摘した不適合事項の是正が1年を超えると認められた場合、又は、是正の見込みがないとき、その他、JAS法に定める認定の取消し要件に該当したときは、認定の取消しを行います。 |
認定工場等を維持するための認定事業者の義務について(一部)
①認定事項が、認定の技術的基準の要求事項等に適合するように維持すること。
②格付の表示に係るJAS法を遵守すること。
③認定事項の変更等の事前に届出ること。
④認定を受けている旨の広告又は表示に係る注意を遵守すること。
⑤格付を担当する者は、定期的(3年毎)に講習会等を受講すること。
⑥全木検の審査等に係る指示に従うこと。
①認定事項が、認定の技術的基準の要求事項等に適合するように維持すること。
②格付の表示に係るJAS法を遵守すること。
③認定事項の変更等の事前に届出ること。
④認定を受けている旨の広告又は表示に係る注意を遵守すること。
⑤格付を担当する者は、定期的(3年毎)に講習会等を受講すること。
⑥全木検の審査等に係る指示に従うこと。
| Q 1-10 JAS認定を取得する費用はどの位ですか。 |
認定取得費用の例
Bタイプの構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目を同時に申請する場合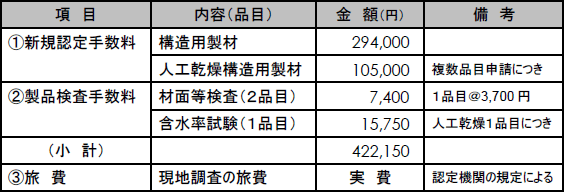 上記の費用を認定審査開始前にお支払いいただきます。
上記の費用を認定審査開始前にお支払いいただきます。
2
Bタイプの構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目を同時に申請する場合
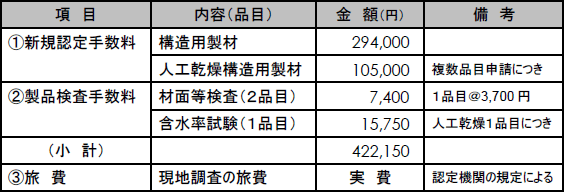
格付けのための検査費用の例(Bタイプの場合のみ)
Bタイプの認定事業者は、格付けの検査を第三者検査機関に依頼する費用が発生します。検査は、1種検査(20日以内)から実施し、5回連続合格後に2種検査(50日以内)に移行します。
構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目を取得している場合(全木検第三者検査機関の例。地方の場合は都府県木(協)連にお問い合わせください。)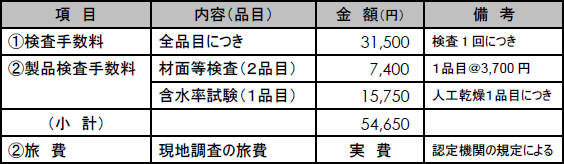
3
Bタイプの認定事業者は、格付けの検査を第三者検査機関に依頼する費用が発生します。検査は、1種検査(20日以内)から実施し、5回連続合格後に2種検査(50日以内)に移行します。
構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目を取得している場合(全木検第三者検査機関の例。地方の場合は都府県木(協)連にお問い合わせください。)
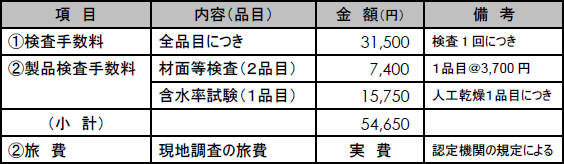
認定の維持費用の例
JAS認定の有効期限の定めはありませんが、認定取得後概ね1年に1回、認定事業者としての要件が維持されていることの確認(監査)が行われます。
Bタイプで構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目の認定を取得している場合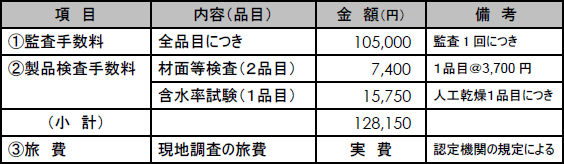
JAS認定の有効期限の定めはありませんが、認定取得後概ね1年に1回、認定事業者としての要件が維持されていることの確認(監査)が行われます。
Bタイプで構造用製材及び人工乾燥構造用製材の2品目の認定を取得している場合
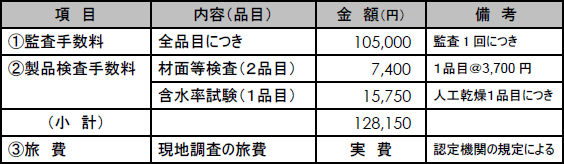
| * | 費用については、製材のJAS制度/3.JAS認定の取得/(3)認定申請書の提出/添付資料「認定、監査手数料」を参照ください。 |
| Q 1-11 「製材のJAS規格解説書」はどこで手に入りますか。 |
「製材の規格及び解説」の販売は、日刊木材新聞社(TEL.03-3820-3511,FAX.03-3820-3518)、全木検、都府県木(協)連の窓口で取り扱っています。
なお、現在、販売しているポケット版は、次の2冊です。
なお、現在、販売しているポケット版は、次の2冊です。
| ・ | 一般製材については、「新しい製材の日本農林規格並びに改正の要点及び解説」 発行 平成23年1月 定価3,200円(消費税込み) |
| ・ | 2×4製材については、「枠組壁工法構造用製材の日本農林規格並びに解説」 発行 平成23年1月 定価2,800円(消費税込み) |
| Q 2-1 輸出用木材こん包材とはどのようなものですか。 |
国際貿易において木材こん包材を規制する要件について
国際植物防疫条約に基づく「植物検疫措置に関する国際基準第15」において、「非加工の生材で作られる木材こん包材は、有害動植物が侵入及びまん延する経路となる。木材こん包材の原産地を確定することは困難であることが多いため、有害動植物のまん延の危険度を有意に減少させるための世界的に承認された措置について記述する。」と定義しています。
2
国際植物防疫条約に基づく「植物検疫措置に関する国際基準第15」において、「非加工の生材で作られる木材こん包材は、有害動植物が侵入及びまん延する経路となる。木材こん包材の原産地を確定することは困難であることが多いため、有害動植物のまん延の危険度を有意に減少させるための世界的に承認された措置について記述する。」と定義しています。
規制される木材こん包材について
輸出貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材をいいます。さらに、木材こん包材は、樹皮を除去した木材を使用し作成すること(ただし、樹皮の大きさが、長さに関係なく幅3cm未満であるものや、幅が3cm以上であっても各々の表面積が50cm2未満であれば差し支えない。)とされています。
また、規制対象外の一例として、接着剤、加熱加圧、又はそれらを組み合わせて作られる合板などの木材製品だけでつくられた木材こん包材は、この規制から除外されます。
なお、規制対象品については、「輸出用木材こん包材消毒実施要領」を参照ください。
3
輸出貨物(携帯品及び郵便物を含む。)の保持、保護又は運搬に用いる木材又は木製品(紙製品を除く。)で、クレート、木箱、荷箱、ダンネージ、パレット、ケーブルドラム、スプール、リール等を含む非加工木材をいいます。さらに、木材こん包材は、樹皮を除去した木材を使用し作成すること(ただし、樹皮の大きさが、長さに関係なく幅3cm未満であるものや、幅が3cm以上であっても各々の表面積が50cm2未満であれば差し支えない。)とされています。
また、規制対象外の一例として、接着剤、加熱加圧、又はそれらを組み合わせて作られる合板などの木材製品だけでつくられた木材こん包材は、この規制から除外されます。
なお、規制対象品については、「輸出用木材こん包材消毒実施要領」を参照ください。
木材こん包材の消毒処理について
輸出用木材こん包材の消毒は、熱処理による方法と臭化メチルくん蒸処理による方法とが規定されていますが、オゾン層保護の観点から、原則として熱処理を用いることとしています。
熱処理は、木材こん包材の材芯温度が56℃以上で30分以上保持するよう加熱されることが条件としています。
熱処理施設は、蒸気式加熱、遠赤外線過熱方式等の恒温加熱乾燥方式または蒸煮加熱方式の2種類があります。
認定消毒実施者は、消毒処理済み木材の消毒実施記録(材種、寸法、自動温度記録装置による等処理経過を示す記録)を熱処理依頼者に交付するとともに、木材こん包材に消毒処理済みであることを示す目印を付すことが必要です。
4
輸出用木材こん包材の消毒は、熱処理による方法と臭化メチルくん蒸処理による方法とが規定されていますが、オゾン層保護の観点から、原則として熱処理を用いることとしています。
熱処理は、木材こん包材の材芯温度が56℃以上で30分以上保持するよう加熱されることが条件としています。
熱処理施設は、蒸気式加熱、遠赤外線過熱方式等の恒温加熱乾燥方式または蒸煮加熱方式の2種類があります。
認定消毒実施者は、消毒処理済み木材の消毒実施記録(材種、寸法、自動温度記録装置による等処理経過を示す記録)を熱処理依頼者に交付するとともに、木材こん包材に消毒処理済みであることを示す目印を付すことが必要です。
木材こん包材消毒処理済みの表示について
登録こん包材生産者は、消毒処理済みの輸出用木材こん包材に登録を受けたスタンプ等で表示します。
表示は、明瞭に判読できること、恒久的かつ取り外せない方法で、一面と反対側の面の少なくとも2面に付される必要があります。
登録こん包材生産者は、消毒処理済みの輸出用木材こん包材に登録を受けたスタンプ等で表示します。
表示は、明瞭に判読できること、恒久的かつ取り外せない方法で、一面と反対側の面の少なくとも2面に付される必要があります。
| Q 2-2 | 認定消毒実施者になるには、どうすればよいのですか。認定工場は何を求められますか。 |
輸出用木材こん包材に係る資格者について
輸出用木材こん包材に係る資格は、木材を消毒する資格者・認定消毒実施者と消毒済み木材を使用してこん包材を生産し、消毒処理済みの表示を行うことができる資格者・登録こん包材生産者があります。
この資格は、それぞれ農林水産省消費・安全局長の登録を受けた消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会ほか)による認定または登録を受ける必要があります。
2
輸出用木材こん包材に係る資格は、木材を消毒する資格者・認定消毒実施者と消毒済み木材を使用してこん包材を生産し、消毒処理済みの表示を行うことができる資格者・登録こん包材生産者があります。
この資格は、それぞれ農林水産省消費・安全局長の登録を受けた消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会ほか)による認定または登録を受ける必要があります。
認定消毒実施者の認定申請について
消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会、等)に対し、所定の申請書に、認定申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を添えて提出します。
全国木材検査・研究協会は、熱処理消毒(HT)(加熱乾燥方式または蒸煮加熱方式)に係る範囲のみ認定対象とします。臭化メチルくん蒸(MB)は対象としません。
申請用紙は、全国木材検査・研究協会に申込むか、このホームページからコピーしてください。(「認定の手続き」参照)
3
消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会、等)に対し、所定の申請書に、認定申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を添えて提出します。
全国木材検査・研究協会は、熱処理消毒(HT)(加熱乾燥方式または蒸煮加熱方式)に係る範囲のみ認定対象とします。臭化メチルくん蒸(MB)は対象としません。
申請用紙は、全国木材検査・研究協会に申込むか、このホームページからコピーしてください。(「認定の手続き」参照)
認定の基準について
消毒証明実施機関は、申請書類及び工場調査を行い認定の判定を行います。
認定基準は、ア.処理及び保管施設 イ.製造施設 ウ.品質管理 エ.表示等について要件に適合するか判定します。
製造施設の加熱施設は、基準温度を持続して保持できること、温度計で施設内の温度を測定し、室外で測定値の確認及び記録をして証明できる自動記録計を具備することが必要です。
詳しくは、全国木材検査・研究協会までお問い合わせ下さい。
4
消毒証明実施機関は、申請書類及び工場調査を行い認定の判定を行います。
認定基準は、ア.処理及び保管施設 イ.製造施設 ウ.品質管理 エ.表示等について要件に適合するか判定します。
製造施設の加熱施設は、基準温度を持続して保持できること、温度計で施設内の温度を測定し、室外で測定値の確認及び記録をして証明できる自動記録計を具備することが必要です。
詳しくは、全国木材検査・研究協会までお問い合わせ下さい。
認定の通知について
消毒証明実施機関は、基準に適合すると認定したときは、申請者に書面(認定通知書)で通知し、認定書を交付します。認定の有効期間は3年間です。
ただし、期の途中での認定の場合は、3年目の年度末までとなります。
5
消毒証明実施機関は、基準に適合すると認定したときは、申請者に書面(認定通知書)で通知し、認定書を交付します。認定の有効期間は3年間です。
ただし、期の途中での認定の場合は、3年目の年度末までとなります。
認定消毒実施者の責務について
| ① | あらかじめ申請書に添えて提出した熱処理標準表に基づいて消毒を実施すること。 |
| ② | 消毒処理木材の受け渡しに当たって、消毒実施済みの表示を行い、自動温度記録装置による「熱処理等実施記録」を交付すること。 |
| ③ | 消毒処理木材の樹種、寸法、処理量等を四半期ごとに消毒証明実施機関に報告すること。 |
| ④ | 1年に1回、消毒証明実施機関の定期実地調査を受けること。 |
| Q 2-3 | 登録こん包材生産者になるには、どうすればよいのですか。登録工場は何を求められますか。 |
輸出用木材こん包材に係る資格者について
輸出用木材こん包材に係る資格は、木材を消毒する資格者・認定消毒実施者と消毒済み木材を使用してこん包材を生産し、消毒処理済みの表示を行うことができる資格者・登録こん包材生産者があります。
この資格は、それぞれ農林水産省消費・安全局長の登録を受けた消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会ほか)による認定または登録を受ける必要があります。
2
輸出用木材こん包材に係る資格は、木材を消毒する資格者・認定消毒実施者と消毒済み木材を使用してこん包材を生産し、消毒処理済みの表示を行うことができる資格者・登録こん包材生産者があります。
この資格は、それぞれ農林水産省消費・安全局長の登録を受けた消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会ほか)による認定または登録を受ける必要があります。
登録こん包材生産者の登録申請について
消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会、等)に対し、所定の申請書に、登録申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を添えて提出します。
併せてスタンプ等印影の標章登録申請書を提出します。
申請用紙は、全国木材検査・研究協会に申込むか、このホームページからコピーしてください。(「登録の手続き」参照)
3
消毒証明実施機関(全国木材検査・研究協会、等)に対し、所定の申請書に、登録申請書及び基準不適合等の場合の処置に関する同意書を添えて提出します。
併せてスタンプ等印影の標章登録申請書を提出します。
申請用紙は、全国木材検査・研究協会に申込むか、このホームページからコピーしてください。(「登録の手続き」参照)
登録の判定について
消毒証明実施機関は、申請書類の各事項について必要により工場調査を行い、登録の判定を行います。 確認事項は、
ア.こん包材生産工程の管理責任者
イ.スタンプ等の保管管理責任者
4
消毒証明実施機関は、申請書類の各事項について必要により工場調査を行い、登録の判定を行います。 確認事項は、
ア.こん包材生産工程の管理責任者
イ.スタンプ等の保管管理責任者
ウ.
消毒処理済こん包材の保管場所・方法等について要件に適合するか判定します。スタンプ等の標章登録は、要件を満たしていることを確認し、登録します。
登録の通知について
消毒証明実施機関は、申請内容が適正と確認して登録したときは、申請者に書面(登録通知書)で通知します。登録の有効期間は3年間です。
ただし、期の途中での登録の場合は、3年目の年度末までとなります。
5
消毒証明実施機関は、申請内容が適正と確認して登録したときは、申請者に書面(登録通知書)で通知します。登録の有効期間は3年間です。
ただし、期の途中での登録の場合は、3年目の年度末までとなります。
登録こん包材生産者の責務について
| ① | 消毒実施者の消毒実施記録及び消毒実施済みの表示を確認し、こん包材にスタンプ等の表示を行うこと。 |
| ② | スタンプ等表示実績を帳票等に記録保管し、これを取りまとめて四半期ごとに消毒証明実施機関に報告すること。 3年に1回、消毒証明実施機関の定期実地調査を受けること |
| Q 2-4 消毒者の認定取得費用、生産者の登録費用はどの位ですか。 |
消毒実施者の認定時に発生する認定手数料(次表①)と、認定取得後、概ね1年ごとに消毒処理が適正に行われていることを確認するための定期実地調査の費用(同②)が発生します。
更に、認定の有効期限は3年で、継続して認定を取得する場合、認定の更新手数料(同③)が発生します。
いづれも、実地調査のための旅費(同④)が掛かります。
また、人工乾燥処理材のJAS認定を取得している事業者は、費用が減額されます。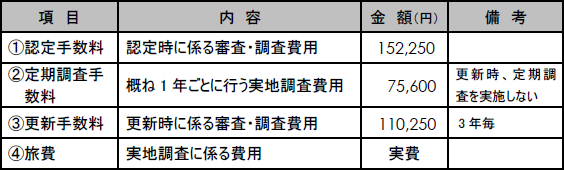
2
更に、認定の有効期限は3年で、継続して認定を取得する場合、認定の更新手数料(同③)が発生します。
いづれも、実地調査のための旅費(同④)が掛かります。
また、人工乾燥処理材のJAS認定を取得している事業者は、費用が減額されます。
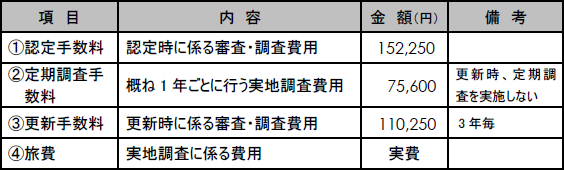
こん包材生産者の登録時に係る費用は特に発生しませんが、年次の管理費が発生します。
更に、登録の有効期限は3年で、その間に1回、木材こん包材の消毒処理の表示が適正に行われている確認のための実地調査に係る旅費が発生します。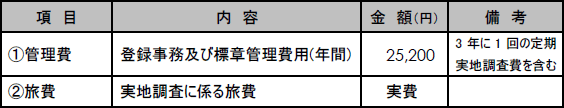 また、スタンプを各自作成することができますが、当協会に登録する必要があります。
また、スタンプを各自作成することができますが、当協会に登録する必要があります。
スタンプの作成を当協会に依頼する場合、標準でプラスチック製 @10,500円。
竹の柄付 @12,100円です。
更に、登録の有効期限は3年で、その間に1回、木材こん包材の消毒処理の表示が適正に行われている確認のための実地調査に係る旅費が発生します。
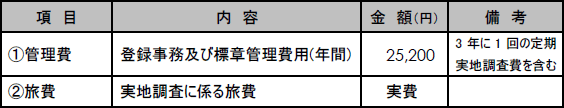
スタンプの作成を当協会に依頼する場合、標準でプラスチック製 @10,500円。
竹の柄付 @12,100円です。
|
|

