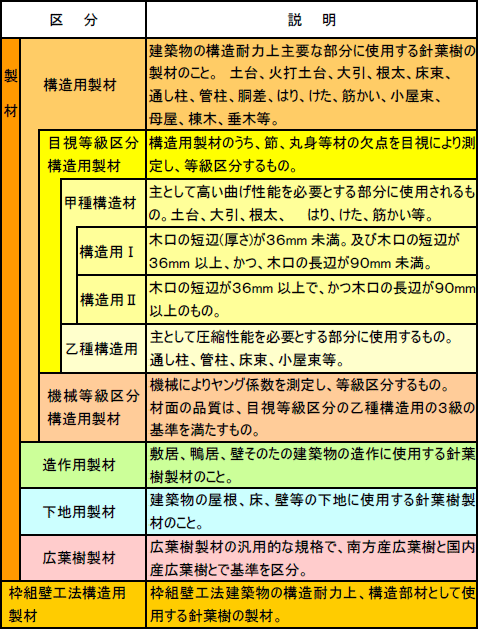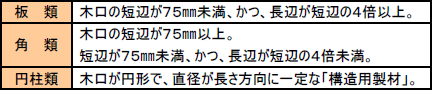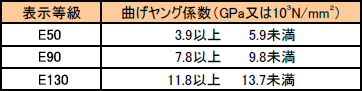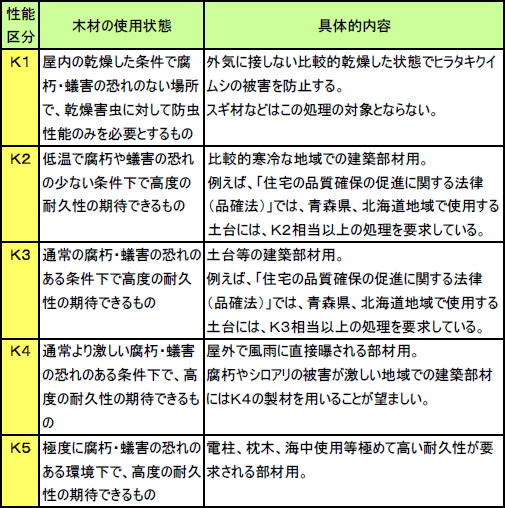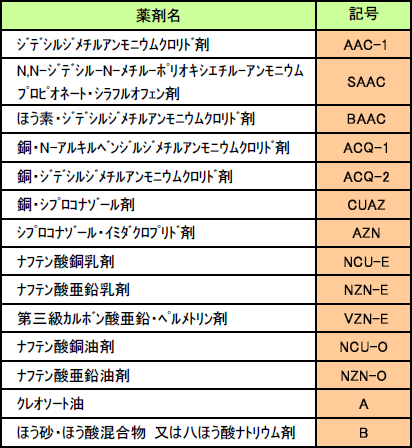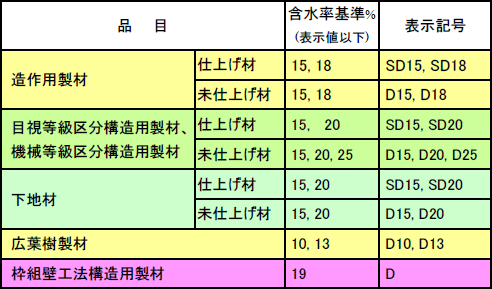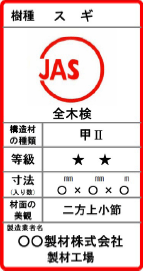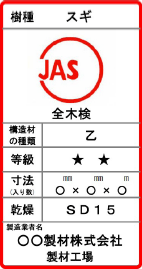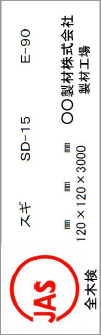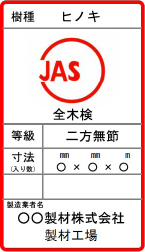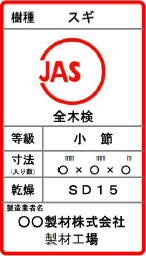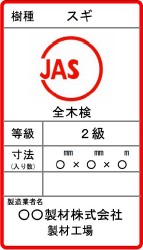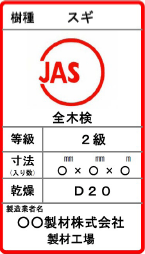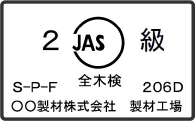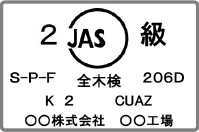|
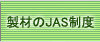 |
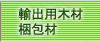 |
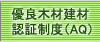 |
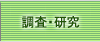 |
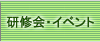 |
 |
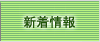 |
|
|
(1)製材のJAS規格
木材は、木造建築の重要な資材として、寸法、材質、強度性能等の品質
が明確で安全性に優れた規格木材の供給が重要な課題であります。
また、地球温暖化防止対策に向けた取り組みの中でも重要な位置付けと して木材利用推進が求められています。 これらに応えるため木造建築物等に使用される構造用、造作用、下地用等の製 材について、それぞれ規格を制定し、施工の合理化、木造住宅及び木造建築物の振興に寄与することを目的として、「製材の日本農林規格」及び「枠組壁工法構造用製材の日本農林規格」が制定されています。
(2)JAS規格の区分
「製材のJAS規格」(平成19年8月29日農林水産省告示第1083号)は、
一般材(次の区分のうち、構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材)、押角、耳付材及びまくら木
(「製材」と総称する。)に係る規格を規定しています。
「枠組壁工法構造用製材のJAS規格」(昭和49年7月8日農林省告示第600号)は、一般材のうち、 枠組壁工法構造用製材に係る規格を規定しています。
(3)JAS規格の基準
製材JAS規格は、上記(2)の区分ごとに、品質と表示について基準を規定しています。
品質基準は、材面の品質(節、丸身、貫通割れ、目まわり、繊維走行、腐朽、曲がり等)、インサイジング、保存処理、含水率、寸法について規定しています。 表示基準は、表示事項、表示の方法、表示禁止事項について規定しています。詳しくは、次のJAS規格を参照してください。 (4)強度性能の表示について
製材JASでは、「構造用製材」の強度等級区分法として「目視による等級区分法」と「機械による等級区分法」の二つの方法が採用されています。
(5)保存処理について
(6)乾燥処理について
(7)JASマークの表示例
|
|
|